
価格
2200円(税込)ページ数
226ページ発行日
2021年5月13日ISBN
978-4-86265-884-5書評・マスコミ掲載
日本経済新聞で紹介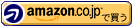
有吉佐和子論 —小説『紀ノ川』の謎—
半田美永
-
『紀ノ川』研究の真髄を観る!
著者の半田美永氏は、有吉佐和子と同郷であり、紀ノ川流域の歴史・地理・民俗等に精通している。「花・文緒・華子」という、明治・大正・昭和三代の系譜を物語る作品として理解されてきた本作を、物語の〈詩と真実〉の落差に注目、第三部の華子のまなざしの行方を問題とした。作品に封印された〈真実〉とは何か、その解明を試みた画期的な一冊である。(明治大学名誉教授・林雅彦)
-
史実に架空の人物を配することによって、新たな《真実》を獲得するというのが、有吉佐和子の物語観であり、史実そのものを超えたところに、彼女の作品世界が構築される。このような創作態度は、彼女のほぼ作品の全てにみられることであり、学問的に未解決な歴史的事象こそが、作品の素材として選択されることになる。(序章より)
目次
-
プロローグ
小説「紀ノ川」の謎 ―〈虚〉と〈実〉の綾織り
序章 有吉佐和子の創作態度
Ⅰ章 小説「紀ノ川」に描かれた〈虚〉と〈実〉
Ⅱ章 豊乃から花へ、そして華子へ
Ⅲ章 長編「紀ノ川」に吸収された短編小説「死んだ家」
Ⅳ章 華子の立ち位置 ―歌舞伎・舞踊との関わり―
終章 物語の詩と真実
補注
主な参考文献
英文紹介
エピローグ
付章・資料
ⅰ 歌舞伎関係資料 ―アメリカ留学時代―
はじめに/①渡米歌舞伎あれこれ/②「夕鶴」のことなど―アメリカ通信/③ブロードウェイで見た歌舞伎/④吾妻徳穂よどこへ行く/おわりに―「解説」にかえて
ⅱ 訪問記 ―「歌舞伎の話を訊く」(抄)―
はしがき/歌舞伎研究家・渡邊美代子/英人歌舞伎研究家・A・C・スコット/「旅」の編集長・戸塚文子/女流作家・眞杉靜枝/婦人代議士・山口シヅヱ/米人歌舞伎ファン・ロムバルディ/衣装研究家・花森安治/随筆家・幸田文/日本舞踊家・西崎綠/ニッポンタイムス記者・R・A・カーズン/随筆家・小堀杏奴/女流作家・網野菊/声楽家・佐藤美子/むすび ─有吉佐和子文学への反映
ⅲ 物語と演劇の融合 ―初期資料拾遺―
はしがき/【1】伝統美への目覚め―わが読書時代を通して―/【2】生きている歌舞伎/【3】事実と芝居と/【4】わが文学の揺籃期 偶然からの出発/【5】ゴージャスなもの/【6】〝老い〟をみつめるのは辛い/【7】いい舞台に期待して/【8】『演劇界』は私にとって育ての親/むすび ─有吉佐和子の外地経験と演劇
略年譜
あとがき
著者略歴
-
半田美永(はんだ よしなが)
昭和22年(1947)8月、和歌山県生。皇學館大学大学院博士課程修了。
専攻、国文学(近代文学)。職歴、講談社子規全集編纂室、智辯学園和歌山中学・高等学校教諭、皇學館大学教授を経て、平成30年(2018)3月、皇學館大学特別教授を任期満了退職。博士(文学)。
現在、皇學館大学名誉教授。中国河南師範大学客員教授。
主要単著 『劇作家阪中正夫―伝記と資料』(和泉書院、昭和63年)、『佐藤春夫研究』(双文社出版、平成14年)、『文人たちの紀伊半島』(皇學館出版部、平成17年)、『近代作家の基層―文学の〈生成〉と〈再生〉・序説』(和泉書院、平成29年)。
共編著『紀伊半島近代文学事典』(和泉書院、平成14年)、『有吉佐和子の世界』(翰林書房、平成16年)、『丹羽文雄と田村泰次郎』(学術出版会、平成18年)、『丹羽文雄文藝事典』(和泉書院、平成25年)、『日本俳句入門』(上海世界図書出版公司、令和2年)他。歌集『中原の風』(平成20年、短歌研究社)等。
国際熊野学会理事(副代表)、子規研究の会理事(会長)、伊勢日赤病院倫理委員等。放送大学、明治大学リバティアカデミー、早稲田大学エクステンションセンター等の講師を務める。

